「やさしくて部下思いの上司でラッキー!」と思ったのも束の間、なかなか仕事を任せてもらえない、自立がしづらいなど、成長の機会が少ないことに危機感を覚えている人はいませんか? 「ホワイトハラスメント」という言葉も生まれていますが、新人や若手社員が職場で成長するためには何が必要なのでしょう。
- この記事でわかること
-
- やさしすぎる上司のもとで働くデメリット
- ホワイトハラスメントの意味や具体例
- 若手社員がスキルアップすべき理由
- 自己アピールにつながる自己投資
やさしすぎる上司のもとでは成長の機会が少ないって本当?
新社会人や若手社員にとって、成長の機会が少ない環境はキャリアの足かせになることもあります。「やさしい上司が、実は部下の成長を妨げることがある」と聞くと、驚く人もいるかもしれません。
もちろん、やさしい上司が必ずしも悪いわけではありません。親切に相談にのってくれる、丁寧な指導をしてくれるなど、やさしさが部下を導くシーンは多々あります。ところがやさしすぎる上司には、部下の成長を阻害するリスクがあるのです。
やさしすぎる上司の特徴や行動
やさしさも行き過ぎればデメリットを招きます。やさしすぎる上司には、次のような特徴が見られます。
- やさしすぎる上司の特徴
-
- 「大変だよね」「手伝ってあげるね」と、部下の仕事を奪う
- 「私がやっておくから大丈夫」と、部下に仕事を任せない
- 失敗しないように、簡単な仕事ばかり任せる
- 業務上必要でも、部下への注意や指導に消極的
- フィードバックが甘く、気づきを促せない
- 責任が伴う仕事は、ベテランだけに任せる
最初は上司のやさしさをありがたく感じるかもしれませんが、上記のような状態が続くと「いつまでも簡単な業務ばかりでスキルが身につかない」「いつまで経っても独り立ちできない」という状況になってしまいます。新入社員や若手社員が成長するためには、経験が欠かせません。やさしすぎる上司は、部下に経験を積ませることが苦手ともいえるでしょう。
ホワイトハラスメントとは?意味や用例を紹介
実は近年、「ホワイトハラスメント(ホワハラ)」という概念が注目されています。ホワハラとは「過度な配慮とやさしさが、かえって相手の成長や自由を奪う」 という問題を指します。
ホワイトハラスメントの具体例
ホワハラはまだ新しい概念ですが、次のような状況がホワハラとして扱われることがあります。
- ホワハラの例
-
- 「大変な仕事だから、先輩に任せていいよ」と、本人が意図せず仕事の機会を奪われる
- 「失敗したらかわいそうだから」と、重要な仕事を任せてもらえない
- 「まだ若いから無理しなくて大丈夫」とキャリアアップ・スキルアップの機会をもらえない
一見、部下を配慮した行動に見えますが、挑戦の場や成長の機会を奪われる状況になっているのがホワハラです。ホワハラという概念が生まれた背景には、パワハラ防止や働き方改革などの影響も考えられます。決して悪意のある行動ではなく、むしろ「新入社員や若手社員を大切に育てていきたい」という考えのあらわれであることも多いです。
ホワイトハラスメントはパワハラで訴えてもいいの?
やさしすぎる上司のもとで働いている人は、ホワハラに悩むケースが増えています。それでは、ホワイトハラスメントをパワハラとして訴えることはできるのでしょうか? 結論から言うと、ホワイトハラスメントをパワハラとして法的に訴えるのは難しいといえます。
パワハラの定義(厚生労働省より)
職場のパワハラを検討するときは、厚生労働省の6類型を参考にしてみましょう。
- パワハラの6類型
-
- 精神的な攻撃(過剰な叱責、罵倒など)
- 身体的な攻撃(叩く、殴る、蹴るなど)
- 過大な要求(能力やポジションに対して多すぎる仕事量)
- 過小な要求(能力やポジションに見合わない仕事、過小評価)
- 人間関係からの切り離し(無視、孤立させようとするなど)
- 個の侵害(プライベートの詮索や家族の悪口など)
ホワイトハラスメントは、相手を配慮しすぎたことによる行為を指す概念であり、直接的に精神的・身体的な被害を与えるものだとは断定できません。パワハラと判断するのは慎重になるべきです。ただし、パワハラの類型の中には「過小な要求」があり、ホワハラがパワハラに該当する可能性がゼロともいえません。とはいえ、「やさしすぎる上司から、過小な要求というホワハラを受けている!」と判断して、上司を責めるのはちょっと待ちましょう。
あなたが現状に不満を抱いていても、上司や会社に合理的な理由が認められる可能性も高いのです。新入社員や若手社員には、まずは会社に慣れること、基礎知識を身に付けることなども必要。上司や会社が想定する成長のスピードと、あなたが望むスピードにズレを感じることもありえます。
それでも、やさしすぎる上司との関係性をこのままにするのは辛い……という人もいますよね。「成長の機会がもっと欲しい」という希望を上司に伝え、改善を求めることは可能です。
成長につながる自己アピール5選
やさしすぎる上司は、「あなたに仕事を任せても大丈夫」という確信がもっと欲しいのかもしれません。ここでは、上司からの信頼を得るための自己アピール方法を5つ紹介します。
やる気を言葉で表現する
上司が「誰かこの仕事をやってくれないかな?」と提案したとき、「やってみたいです」と言葉でやる気を伝えていますか? 上司は部下が思っている以上に多忙です。やる気はあっても心に秘めている人、上司が気づいてくれるのを待っている人には、チャンスはなかなか巡ってきません。やる気は言葉にして上司に伝えていきましょう。
上司に直接相談する
「成長したいけど、何をすればいいかわからない」というときは、上司に相談するのも一つの手です。「新しい仕事にも挑戦したいんですけど、どんな人なら任せたいと思いますか?」とストレートに相談することで、上司があなたの気持ちに耳を傾けてくれることも。
小さな信頼を積み上げる
仕事を任せてもらうには、まずは小さな信頼を積み上げることが大切です。
- 小さな信頼の例
-
- 資料作成やプレゼンを引き受ける
- 業務の効率化を提案する
- 先輩の指導をよく聞き、仕事に活かす
- 報連相で仕事を見える化する
こうした行動を積み重ねることで、「この人なら任せても大丈夫」と信頼が厚くなります。特に大切なのは報連相を欠かさないこと、仕事の見える化をすることです。仕事は一人でできることではありません。自分の頑張りを認めてもらうためにも、チームの一員として貢献するためにも、情報共有をしていきましょう。
自分の強みをアピールする
やさしすぎる上司は、あなたの特技や得意分野を把握しきれていないのかもしれません。「リサーチが得意なので、企画にチャレンジしてみたいです」「データ分析の勉強をしているので、レポート作成に自信があります」など、自分の強みをアピールするのもおすすめですよ。
自己研鑽・自己投資でスキルを磨く
やさしすぎる上司は、あなたの実力を心配している可能性もあります。新入社員や若手社員が仕事で失敗をして、メンタルが不安定になることは少なくありません。安全に育てようとするあまり、やさしすぎる対応になっていることもあるでしょう。上司を安心させるためにも、資格取得やスキルアップを通じて自分自身を成長させるのもおすすめです。
若手社員におすすめ♪仕事に役立つ資格を紹介
新入社員や若手社員の中には、やさしすぎる上司に対してモヤモヤや不満を感じることもあるでしょう。友人や同僚に相談しても「やさしい上司なんてラッキーじゃん!」「そういう悩みでうらやましいよ」と相手にしてもらえず、解決策が浮かばないという人もいるはず。やさしすぎる上司のもとで成長するためには、「仕事を任せてもらえる自分」になることが大切です。
いわば、自分自身のスキルアップさせるのです。成長意欲をアピールするなら、仕事に役立つ資格を取得し、自己投資を始めるのもおすすめですよ。
TOEIC
近年はインバウンドの需要も高く、グローバルな取引をする企業がますます増えています。英語のスキルアップを図ることで、強みを磨くことができます。TOEICはビジネスシーンの英語力を測定する試験です。仕事に役立つスキルとしてアピールするなら、最低でもスコア700以上を目指し、より高得点を狙って勉強しましょう。
MOS
MOSとは、「マイクロソフト オフィス スペシャリスト」の略で、PC操作スキルを証明できる資格です。資格取得の勉強を通して、ExcelやWord、PowerPoint、Outlook、そしてAccessの操作を理解できます。特にAccessはデータベースやマーケティングなど、分析や業務効率化に貢献できるスキルです。
簿記
簿記は、企業の会計や税務の理解、資金の流れの管理に役立つ資格です。経理部や経営企画、営業はもちろんですが、さまざまな職種で簿記の知識を活かすことができます。若いうちに簿記の知識を習得することで、将来的なキャリアアップや転職でも役立つでしょう。
ITパスポート(基本的なIT知識を証明)
ITパスポートは、情報処理技術者試験の中で入門レベルに位置づけられる国家資格です。ITに関する基礎的な知識のほか、業務フローや進捗管理の知識も学習します。ITパスポートの資格を取得することで、スキルアップの意欲やIT技術への関心をアピールできます。
まとめ:やる気×自己投資でデキる若手社員に♪上司からの信頼も得られる!
やさしすぎる上司のもとでモヤモヤしている人は、やる気をエネルギーに変えて自己投資をしてみましょう。小さなチャレンジを積み重ねて、上司の信頼を得ることが大切。資格取得も組み合わせれば、成長速度がアップするはずですよ。
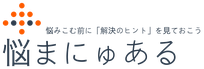
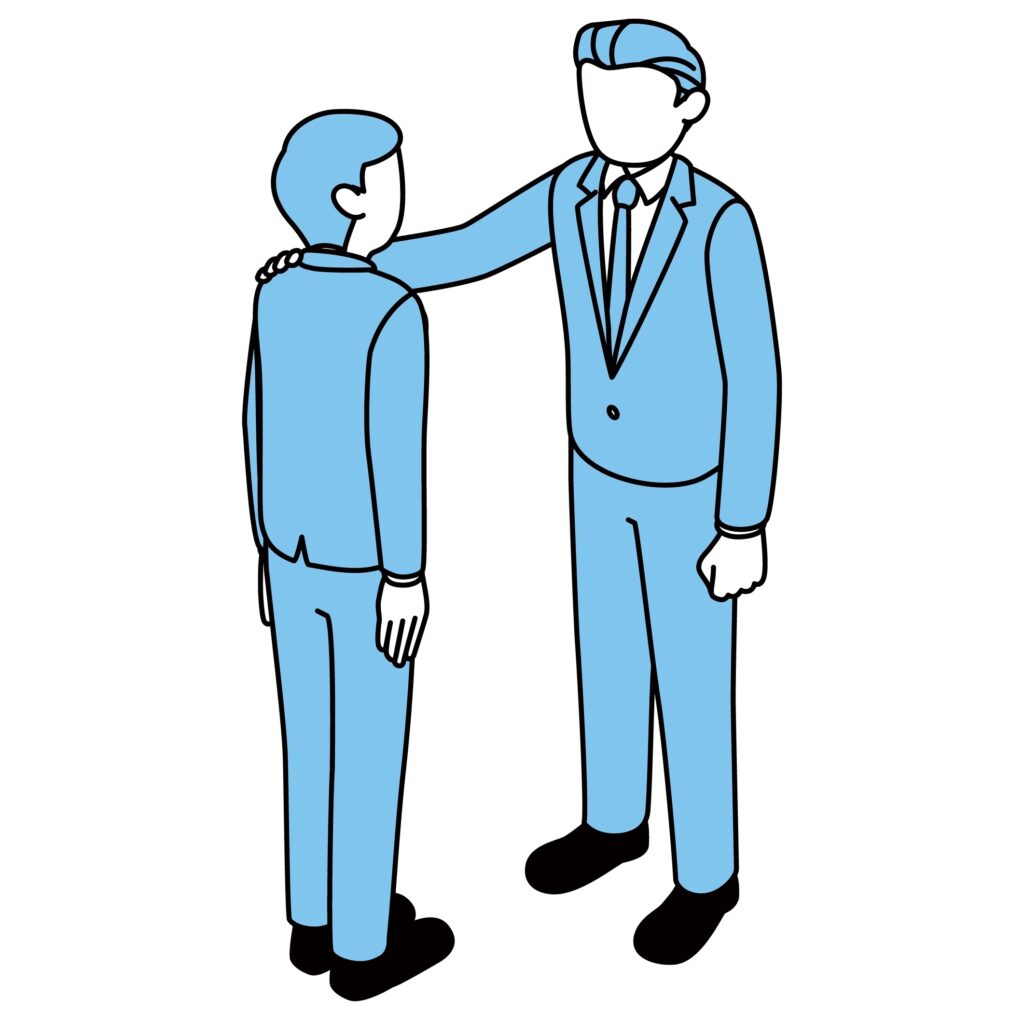




コメント