条例とは各自治体で定めるルールですが、実は法律と条令にはそれぞれ特徴があります。この記事では条例とは何か、各地域の条例はどんな特色を持っているのか、を説明します。記事を読んだ後は、お住まいの自治体の条例を調べたくなるはずです!
- この記事でわかること
-
- 法律と条例の違い
- 法律違反・条例違反したらどうなる?
- 条例が持つ特徴や意義
- 日本の地域ならではのご当地条例
条例と法律の違いとは?
条例と法律は同じものではありません。それぞれの成り立ちなどが違いますので、基本的なところを確認していきましょう。
条例とは?
条例とは、都道府県や市区町村といった地方自治体が制定する「地域ごとのルール」です。地方議会(都道府県議会や市町村議会など)が議決する「自治立法」とも呼ばれています。たとえば、子どもがタバコやお酒を買わないようにする「未成年飲酒禁止条例」、自転車のヘルメット着用を義務付ける条例など、各地域の特色や課題解決、まちおこしなど目的に合わせた内容になっています。
そのため、ある地域の条例が全国で適用されるわけではありません。条例によって決められる事項は、国が制定する法律よりも限定的です。その分、地域のニーズや状況に応じて柔軟かつきめ細かく定めることができます。
法律とは?
法律とは、国会で制定される「国全体に適用されるルール」です。憲法に基づき、国会の議決を経て制定されます。法律はさまざまな種類があることはご存知ですか? 民法や刑法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、行政法などは聞いたことがある人が多いでしょう。
さらに交通事故に関する道路交通法、働く環境を整える労働基準法、学校教育法、消防法など、目的に応じて法律が整備されています。憲法を含めた約1,900の法律が制定されており、政令や省令も含めるとさらに膨大な数になります。
人々が持っている権利や財産、安全などを守るために、多種多様な法律が制定されているというわけです。どこに住んでいても日本国内にいる限り、同じ法律が適用される点は、条例とは異なります。
条例に違反したら罰則はあるのの?
条例に違反した場合、必ずしも罰則が科されるわけではありません。罰則規定が定められている条例もありますが、多くの場合、違反者に対して「勧告」や「指導」などの措置を行うにとどまることが多いです。しかし、悪質な違反や、条例で罰則を明確に定めている場合には、罰金などが科されることもあります。
ただし、条例で定めることのできる罰則には上限が定められています。
- 条例の罰則の上限
- 2年以下の懲役もしくは禁錮、100 万円以下の罰金、拘留、科料(かりょう)もしくは没収の刑、5万円以下の過料
法律に違反したら必ず罰せられるの?
法律に違反すると刑罰が科されることがあり、罰金や懲役、禁錮といった処罰が法律違反者に課されることもあります。法律に違反したからといって、必ず罰則が科せられるとは限りません。法的拘束力のない努力義務規定に違反した場合は、罰則は課されません。ただし、損害賠償が請求される可能性はあります。
日本国内のユニークなご当地条例の具体例
条例と法律の違いを紹介しました。法律は日本全国共通のルールですが、条例は各地で特色が出るのが大きな違いです。今回は、地域の特色が出る条例の中からユニークな条例、いわばご当地条例を紹介します。各地域の魅力や課題が反映されており、地域ごとの考え方や取り組みがわかりますよ。
【奈良県】「奈良県立都市公園条例」
奈良県には、奈良公園があり鹿が有名ですよね。鹿を守るために「奈良県立都市公園条例施行規則」が定められています。この条例は、鹿せんべい以外の動物への餌付けを禁止事項とし、鹿せんべい以外を与えることは条例違反になります。
奈良市観光協会サイトによると、鹿せんぺいの原材料は小麦粉と米ぬかです。砂糖などは一切使用せず、鹿の健康を考慮して作られています。一方、観光客が人間用の食料を鹿にあげてしまうと、鹿の健康を損なうおそれがあるというわけです。観光客が多い奈良県ならではの条例であり、シカとの共存を目指す取り組みの一環ですね。
【東京都渋谷区】「渋谷駅周辺地域の安全で安心な環境の確保に関する条例」
渋谷区では毎年10月のハロウィン、年末のカウントダウンなど混雑する時期は厳戒態勢がしかれていました。大混雑や騒動が原因で、渋谷駅周辺の安全が守りにくい状況となっていたことが問題視され、「渋谷駅周辺地域の安全で安心な環境の確保に関する条例」が令和元年に制定されました。
ただし迷惑路上飲酒やごみの放置はまだまだ問題として残っており、令和6年10月1日には、午後6時から翌朝5時の間、路上や公園など公共の場所における飲酒を通年で禁止し、また禁止エリアも拡大する内容へと改正されました。
【京都府】「京都府景観条例・京の景観ガイドライン」
京都市では伝統的な街並みを守るための景観保護条例を定めるとともに、「京(みやこ)の景観ガイドライン」を制定し、建物の高さ制限や外壁の色、看板の設置方法に至るまで細かいルールを設定しています。
全国チェーンのコンビニなど企業もこの条例・ガイドラインを守っているため、他の地域では使用していないカラーで店舗デザインがされているなど、京都らしい町並みを守る取り組みを実践しています。まちの人が慣れ親しんだ街並みを守るとともに、地域のブランディングにも役立っています。観光客にとっても、京都の伝統的な雰囲気が味わえるメリットがある条例です。
おわりに:法律と条令は異なる性質を持つ! 地域に根差す条例にも目を向けよう
法律と条例は似ているようで違い、条例が持つユニークさを紹介しました。法律を守ることも大切ですが、条令にも目を向けることで地域の課題や魅力をもっと理解できるようになりますよ。
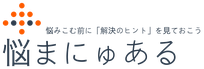




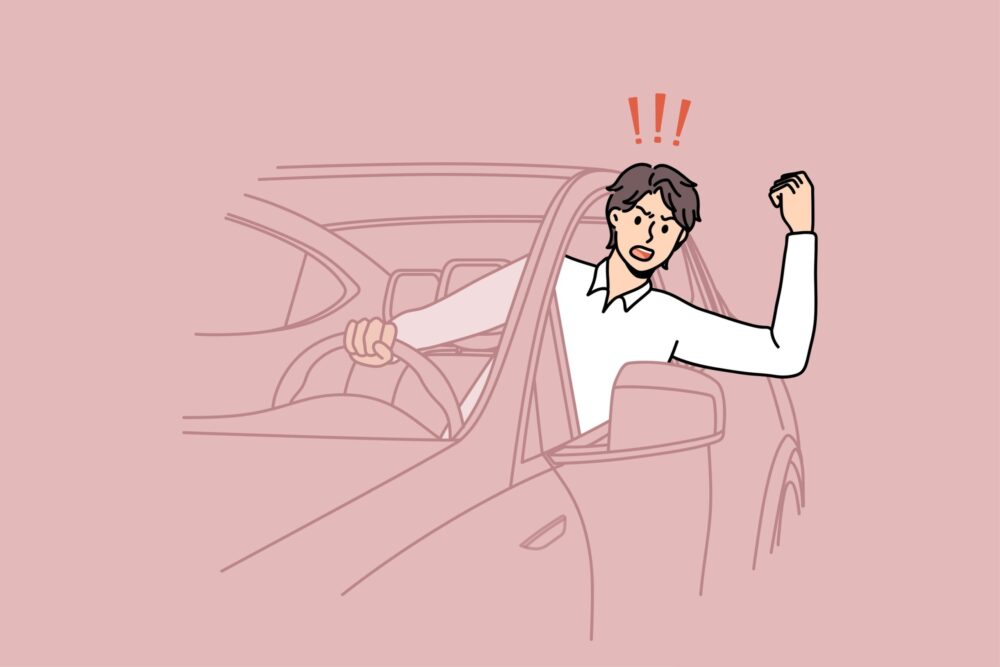
コメント